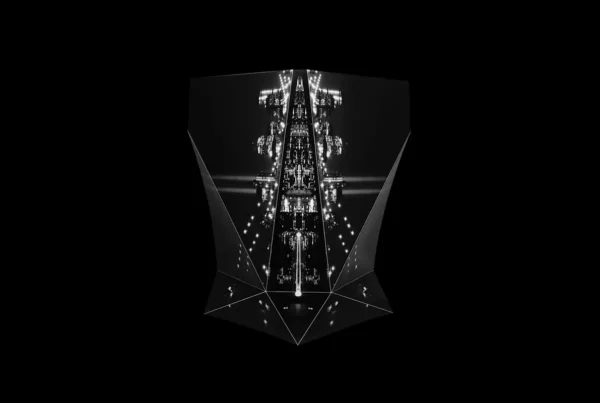「アートは心の傷にそっと手を添えてくれるものです。自分自身を撮りはじめてからは、カメラの前で声を持たない俳優になったような気がしました」
ステージとシャッター、そのあいだに広がる世界
カナダ、サスカチュワン州オールド・ヌタナ。ニレの木が並ぶ静かな通りで育ったモーリーン・ザカルキ(Maureen Zacharki)は、写真と演技、そして語りを組み合わせた独自の表現を追求するアーティストです。舞台で培った感覚と、人生の中で直面してきたさまざまな出来事が彼女の作品を形づくり、観る者に静かな衝撃を与えます。彼女の表現は、最初から写真一筋だったわけではありません。演劇の世界に身を置き、やがて撮る側へと重心を移していく中で、自然とジャンルの枠を越えた視点が育まれていきました。カナダでは雄大な自然を題材にした写真が主流とされていますが、ザカルキの目が向いているのは、自分の内面にある風景です。記憶や痛み、想像の中に広がる感覚を、そっとすくい取ってレンズに収めています。
高校時代、彼女は美術や写真に没頭していました。暗室でネガを現像したり、スケッチを描いたりと、日々、創作に没頭していたといいます。その後、演技の道を選んだことで周囲を驚かせましたが、舞台美術の知識やマイズナー・テクニックの訓練は、後に写真作品にも深く影響を与えることになります。画面の構成や感情の流れを丁寧に設計するその手法には、演劇的なリズムが通っています。ザカルキは、ひとつの物語を組み立てるように、撮影のテンポや間合いにも注意を払っているのです。複数の表現領域で培った経験が、視覚的な語りとして静かに息づいています。
写真が本格的な表現手段となったのは、三叉神経痛という病を発症してからのことでした。顔面に激しい痛みをもたらすこの病に苦しむなか、セルフポートレートは、自分の内面を見つめ直すための行為となりました。カメラは、ただ映すだけの道具ではなく、自分自身と向き合い、語り合う存在になっていったのです。外からは見えない痛みや感情を可視化するこのプロセスは、彼女にとって心の整理でもありました。現在の作品には、はっきりとした輪郭と曖昧さ、美しさと違和感が同時に存在しています。ぴたりととらえきれない感覚を、そのまま写真に封じ込めることで、観る者に新たな問いを投げかけます。ザカルキの写真は、いつもどこか不安定で、だからこそ真実に近い。目には見えない世界を、静かに映し出しているのです。

モーリーン・ザカルキ:写真という名の演技
ザカルキの写真には、舞台で磨かれた感覚が確かに息づいています。光の使い方や身体の動き、そして画面の中に流れる物語性は、舞台表現の経験から生まれたものです。彼女の写真には演出された印象がある一方で、観る者の心に迫るような真実味も同時に宿っています。若い頃から彼女が魅了されてきたのは、ファッション写真の作り出す世界でした。『エル』や『ヴォーグ』といった雑誌のエディトリアルに強く惹かれたザカルキは、衣装デザインを学ぶ中で、視覚的な語りの力に目を開かれていきます。その影響はいまも、写真を組み立てる際の感覚に生きています。心を奪われた作品のひとつとして挙げるのが、サラ・ムーンの『La Robe à Pois』です。ポラロイド風の色彩で描かれた夢のような一場面で、混沌とした空気をまといながらもどこか幻想的。その写真について、彼女は「魔法のようだった」と振り返ります。淡い色合いと現実感のないモデルたちが織りなすその世界観は、今も彼女の創作の原点として胸に残り続けています。
けれど、彼女の表現を形づくる要素はファッションだけではありません。1980~90年代のオルタナティブ音楽の世界を視覚的に定義した、オランダの写真家・映画監督アントン・コービンにも影響を受けています。彼が撮影したジョイ・ディヴィジョンやデペッシュ・モードの写真は、ざらついたモノクロの質感とともに、緊張感のある時間を封じ込めていました。その粗さの中にこそ、ザカルキが求めるリアリティがあったのです。デジタルではその手触りが得られないと感じた彼女は、35ミリフィルムに回帰します。滑らかさではなく、むしろ粒子のある画面にこそ、心の揺れや生々しさが宿ると信じているからです。写真に手を加える編集作業にも積極的なのは、見た目を変えるためではなく、心の内側にある感情により近づけるため。彼女にとって、写真とは「感じたことに形を与える」行為なのです。
なかでも「タブロー写真」と呼ばれる、物語性のある一枚絵のような写真には、強く惹かれるものがあります。たとえば、19世紀のイギリスで活動したジュリア・マーガレット・キャメロン。柔らかいピントと象徴的な構図で知られる彼女の肖像写真には、ザカルキのセルフポートレートに通じる空気があります。静かにたたずむ人物が、どこか物思いにふけりながら、演劇の一場面の途中で時間が止まったかのような感覚を漂わせるのです。ザカルキの写真もまた、観る者をそうした「止まった瞬間」に引き込んでいきます。その中には、言葉にならない痛みや、美しさ、そしてかすかな脆さが、表情の途中にそっと刻まれています。光と影のなかに封じ込められたその一瞬が、彼女の語りかけなのです。

断片とフィルター、そしてキャンバスとしての顔
ザカルキの創作は、彼女自身が抱える神経疾患「アリス症候群」と深く関わっています。空間や時間、物の大きさに対する感覚がゆがむこの稀な知覚障害は、彼女が世界をどう見つめ、どう写真におさめるかに大きな影響を与えてきました。片頭痛の前兆や軽い発作によって視界が歪む体験から、彼女はその感覚を再現する手段として、画像の分割やレイヤーの重ね合わせ、独自の現像方法などを試すようになります。そうした加工は、単なる装飾ではなく、感じたことを視覚に置き換えるための方法です。写真に映るのは、現実の姿ではなく、知覚が揺らいだときの心の風景です。ザカルキの作品は、日常の世界がひび割れて見えるその瞬間を、内面の地図のように描き出しています。
セルフポートレートは、今も彼女の表現の中心にあります。特に三叉神経痛と診断されて以降、写真に自分を写すことは、自分の内側を確かめる行為になりました。顔の片側に続く慢性的な痛みは、まるで顔の中心で自分がふたつに分かれてしまったかのような感覚を生み出したといいます。そこから生まれた作品には、静けさと苦しさが同時に流れ込み、無声映画の俳優のような表情や、20世紀初頭の女優を思わせる佇まいが自然ににじみ出ています。彼女のセルフポートレートは、ただの記録ではありません。過去の映像文化や、身体に刻まれた痛み、自分自身との向き合いが込められた、ひとつの表現行為です。メアリー・ピックフォードやビーブ・ダニエルズといった映画草創期のスターたち、あるいはヴィクトリア朝時代のラファエル前派の女性像は、ザカルキにとって表現の指針となる存在です。
写真の技術的な面でも、彼女の探求心は尽きることがありません。デジタルカメラからインスタントフィルムまで幅広く使いこなし、時には期限切れのポラロイドやレンズフィルターといった不確かな要素も積極的に取り入れます。リー・ミラーが発見したソラリゼーションという手法に影響を受けたザカルキは、写真の効果を小手先の演出とは考えていません。あくまで、自分の感覚を形にするための道具として受け入れています。自然の風景やリアリズムを重視する写真が多いカナダの中で、ザカルキはそうした流れから距離を置き、もっと感情や内面の真実に寄り添う、作り込まれた世界を追求しています。写真は、ただ目の前のものを記録するだけの手段ではない。もっと自由に、かたちを変えながら、新しい視覚の可能性を切り開いていくものだと、彼女は信じています。

モーリーン・ザカルキ:揺らぐ世界で、自分という軸を取り戻す
カナダの写真界で活動を続けるなかで、ザカルキは何度も従来の価値観とぶつかってきました。ある全国誌に、演出を施したフォトエッセイを投稿したときのこと。編集者とのやりとりは順調だったものの、掲載された記事には事実と異なる記述が多く含まれていました。その経験を通して彼女は、定型から外れる表現に対して、芸術の場がいかに閉鎖的であるかを痛感することになります。自然写真が正統とされがちなカナダの文化において、彼女の作品はその枠組みに収まりません。幻想的で、感情の機微に深く踏み込んだ表現は分類の難しいものであり、結果として理解されにくかったのです。あの出来事は単なる失望ではなく、「写真とはこうあるべきだ」という固定観念の根深さを示す象徴のようにも思えました。
しかし、その経験が創作への意欲を削ぐことはありませんでした。むしろ、自分らしい表現を貫こうという思いをいっそう強くしたのです。猫を撮ることもあれば、ユーモアを交えたり、音楽や文学、歴史の断片をそっと作品に忍ばせたりと、彼女はいつも、自分自身が心から惹かれるものに正直であろうとします。一貫したテーマにまとめようとは考えていません。むしろ、思い通りにならない日々の揺らぎこそが創作の源だと捉え、そのときどきの直感や感情に身をゆだねながら、シャッターを切っています。彼女の作品は、ある考えを論理的に展開するものではなく、その瞬間にしか生まれ得ない印象の集まりです。ひとつひとつの写真が、その時々の空気や心の動きを映し出しているのです。
もちろん、その道のりは平坦ではありません。神経疾患や発作の影響で、計画的に物事を進めることが難しくなることもあります。母親や親しい友人の助けを借りながら、彼女は日々の生活を組み立て、作品を発表し、文章を書き、経済的な管理を行い、そして回復の合間にも撮影を続けています。道筋は決してまっすぐではありませんが、その一歩一歩が、自分の人生と語りを自分自身の手に取り戻すための行動となっています。彼女が写真を撮るのは、誰かの期待に応えるためではありません。世界を、少し異なる目で見るとはどういうことなのかを伝えるためです。そして観る人にも、立ち止まってもう一度世界を見つめ直してほしいと願っているのです。もっと丁寧に、もっと好奇心を持って。
モーリーンのMyBioはこちらからご覧いただけます: https://mybio.art/maureen-zacharki