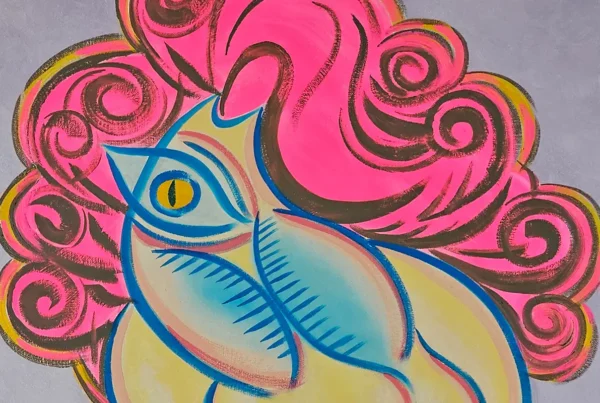「この国で奪われている命がある。その現実に、目を向けてほしいのです。」

商業写真から社会へのまなざしへ
写真家ジェフ・コーウィン(Jeff Corwin)のキャリアは、アートの世界ではなく、商業写真の第一線から始まりました。彼がカメラを向けてきたのは、工業地帯の上空を飛ぶヘリコプターの中、奥地のジャングル、そして航空母艦の甲板の上──常に過酷で予測不能な現場でした。アップル、フェデックス、ボーイング、コカ・コーラ、マイクロソフト、ネットフリックスといった世界有数の企業が、彼のクライアントに名を連ねています。
そうした実績を重ねる中で、コーウィンの写真は、企業のイメージを形づくるものから、社会に対する眼差しを映すものへと少しずつ変化していきます。ファインアートとしての作品制作に重心を移しても、彼のスタイルは一貫しています。商業写真で培った構成力と緻密な技術はそのままに、伝えようとする内容が、より個人的で切実なものへと深まっていったのです。彼の写真は、徹底的にそぎ落とされています。余計な装飾はなく、線や形、光と影といった構成要素だけで画面が成り立っています。その静けさの中には、明確な意思と強い緊張感が漂います。社会的なテーマや感情が込められていても、作品は決して声高にそれを主張することはありません。むしろ、観る者自身に問いを投げかけ、想像力を促すような余白が大切にされています。
これまでに彼の作品は、世界各地で展示されてきました。エディンバラのロイヤル・スコティッシュ・アカデミー、フィンランドのユヴァスキュラ美術館、サンフランシスコのインターナショナル・アート・ミュージアム・オブ・アメリカ、シアトルのフライト博物館など、多様な文化的背景をもつ場で紹介されています。いくつかの作品は美術館のコレクションとして恒久的に収蔵され、国境を越えて人々とつながっています。しかしその根底にある視線は、つねにアメリカという現実に深く根ざしています。写真を通じてコーウィンが語るのは、遠い世界の話ではなく、この国で起きている命の喪失と、それに向き合う責任なのです。

ジェフ・コーウィン:雪に沈む静けさを見つめて
ジェフ・コーウィンの近作には、環境の変化がはっきりと表れています。長く暮らしたシアトルを離れ、現在はモンタナ州ボーズマンを拠点に活動する彼は、アメリカ西部の広大で孤独な冬の風景に触れるなかで、新たな視点を作品に取り込むようになりました。雪に覆われた静かな大地は、余分な情報を排した空間となり、形や構成を際立たせる舞台となっています。冬の静けさは、「引き算の美」を追求する彼の感性と響き合います。そこにあるのは自然賛美ではなく、対比と抑制の中に見出された静かな風景です。
このような風景写真は、一見するとかつての広告写真と技術的に通じるものがありますが、伝えようとしている内容はまったく異なります。初期の作品では、写真は商品やブランドの魅力を伝える手段でしたが、現在の作品にはそうした目的は存在しません。目指しているのは、自分自身の内面を見つめること、そして目の前にあるものを丁寧に観察することです。制作の出発点は単純で、カメラと車があれば足りるということも少なくありません。数時間の外出から数日に及ぶ旅まで、自然と向き合う時間そのものが作品を形づくっていきます。光や天候の移ろいは演出ではなく、被写体をより明確にするための自然な要素として活かされています。
これとは対照的に、「Guns in America」と題されたシリーズは、まったく異なるアプローチを必要とします。自宅に設けたスタジオで制作されるこの作品群では、アメリカ社会における銃による暴力という深刻な問題を視覚化するために、綿密な準備と構成が求められます。ひとつの作品を形にするまでに、長い時間をかけて構想が練られることもあります。アンティークショップで小道具を集め、ミニチュアのセットを組み、光の配置を何度も試しながら、ひとつひとつの要素を調整していきます。その工程は、いずれも意図を持って慎重に進められるものです。こうして生まれる作品は、単なる視覚的批評にとどまらず、コーウィンが長年の商業写真で培ってきた厳密さと集中力を土台に、強い感情と政治的な意識が交錯する表現として結実しています。

引き金をつくる:「Guns in America」の背景にある物語
「Guns in America」というシリーズの出発点には、個人的な経験と社会への問題意識が深く結びついていました。2007年、父の死後に遺品を整理していたコーウィンは、3丁の古い拳銃を見つけます。それは懐かしさではなく、どう向き合うべきかという迷いを生みました。家族の歴史とつながる品でありながら、長年彼が抱いてきた社会的な違和感の象徴でもあったからです。その銃はしばらく手をつけずに保管されていましたが、2012年に起きたサンディフック小学校での銃乱射事件をきっかけに、彼の中で何かが変わりました。もはや目を背けておくことができなくなったのです。友人から「捨てる前に撮ってみては」と提案され、最初は距離を置いていたはずの感情が、次第に強い創作意欲へと変わっていきました。
2013年、コーウィンは初めて一丁の拳銃をスタジオの撮影台に置きました。無地の背景、配置されたライティング。しかし、決定的な手応えを得たのは、錆びた鉄板の上に銃を置いた瞬間でした。ひび割れた黄色の円が、偶然そこに浮かんでいたのです。その視覚的な要素が、彼の考えていたテーマと直感的につながり、作品の方向性が定まりました。この瞬間から、色、光、小道具を通して、アメリカの銃文化に対する違和感を視覚化するシリーズが始まったのです。その後コーウィンは、ジャンクヤードやアンティークショップ、ネット上の市場を巡り、紙幣、時計、弾薬、宗教的なアイテムなど象徴的な品々を集めていきました。それらを用いた写真は、ものと影が重なり合い、寓意を織りなす構成となっています。
このシリーズの作品は、一点ごとに強い意志をもって構成されています。鮮烈な色彩や強い光の演出は、主題の深刻さと切迫感を視覚的に際立たせるためのものです。そこに抑制や曖昧さはありません。なぜなら、描かれている暴力は、特別なことでも一時的なことでもないからです。とりわけ『Guns in America #43』は、コーウィンにとって特別な一枚となりました。考えていたことが、かたちとしてぴたりと定まった瞬間だったと語ります。旗、紙幣、時計といったモチーフを通じて、彼は暴力そのものだけでなく、それを温存する制度や文化の鈍さにも鋭く切り込んでいます。コーウィンのこのシリーズは、壁を飾るための作品ではありません。目を奪い、心に問いを残します。

ジェフ・コーウィン:揺るがぬ眼差しの先に
ジェフ・コーウィンの制作には、まったく異なるふたつのアプローチが共存しています。ひとつは即興性に満ちた動きであり、もうひとつは、徹底した計画と構成によるものです。風景写真の制作は、まず動くことから始まります。機材を車に積み込み、直感と光の変化だけを頼りに出発する。モンタナの冬景色をひとり走る時間は、視覚的な素材を得ると同時に、思考を解き放つ時間でもあります。彼が撮りおさめる風景には、構図、形、感情の響きが一枚の画面に凝縮されており、そこには内面の静けさが映し出されています。観察することの力強さ、視覚の喧騒から解き放たれるような清澄さが、画面のなかに息づいています。
それとは対照的に、「Guns in America」のスタジオワークは極めて緻密で、頭脳を酷使する作業です。一枚の作品をつくるには、数日にわたる手作業と長い思考の積み重ねが必要です。自宅の上階に構えたスタジオは、彼にとっての工房であり、思索に没頭できる静かな場所でもあります。ここで彼は、小さなジオラマを組み立て、光と物の配置を慎重に整えていきます。セットを撮影したあとはすぐに結果を判断せず、一晩おいてから翌日に改めて見直す。この「間」を置くプロセスによって、初めの意図を見失うことなく、必要な修正を加えていきます。こうして生まれる一枚一枚は、思索と実験、そして感情との真摯な対話の積み重ねから導かれています。
今後について、コーウィンはこの二つの制作に、どちらも変わらぬ覚悟で向き合い続けています。冬の風景を見つめる試みは、彼にとって瞑想的な創作の時間をもたらし続けていますが、より強く彼の創作を突き動かしているのは、「Guns in America」に込めた切実な思いです。銃による暴力が絶えないこの国の現状が、シリーズを終わらせることを許さず、新たな作品、新たな問いを生み続けています。これから先の展開がどうなるかはまだわからない──けれどひとつだけ確かなのは、ジェフ・コーウィンの写真が決して目をそらさないということです。雪に覆われた平原の沈黙も、銃という象徴が放つ音なき叫びも、そのレンズはまっすぐに見つめ続けています。