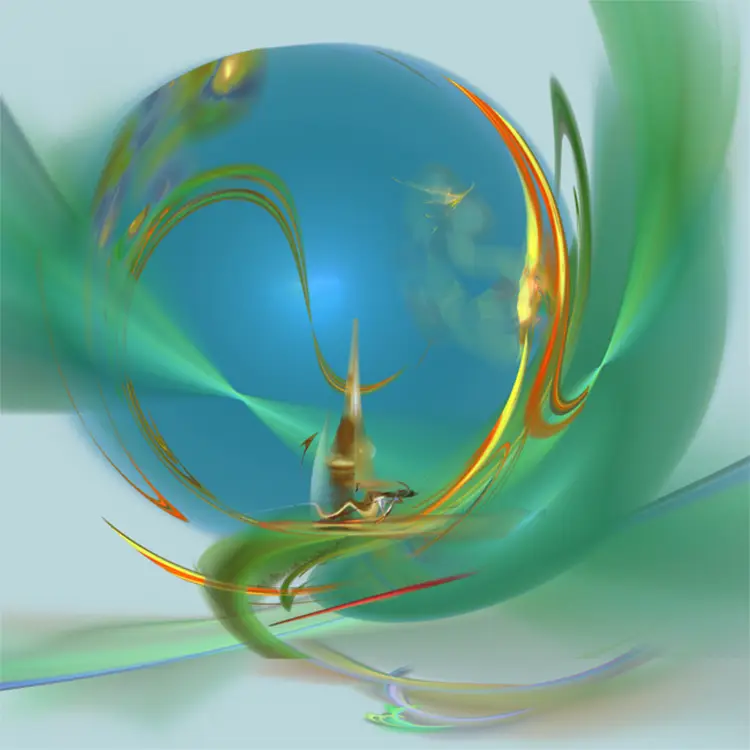著作権 © 2025 ILIA(別名:Leigh Ann Edrich)。無断転載・複製を禁じます。 Leigh Ann Edrich. All Rights Reserved.
「アーティストを止めることなんてできません。私もそうでした。詩や絵は、誰にも見せず、クローゼットの奥にそっと隠していたのです。」
想像がかたちになるまで
イリア(ILIA)の創作は、家族の温もりと草花の気配に包まれた日々のなかで育まれました。母の自由な発想に導かれ、クレヨンや紙粘土で遊んだ幼少期。キッチンのテーブルで夢中になって手を動かすその時間が、彼女にとっての表現の原点でした。とりわけ心に残っているのは、母と一緒に作ったサイエンスフェアの作品。紙粘土でつくった火山が本当に噴火したその瞬間、想像がかたちとなって立ち上がる喜びを、彼女ははじめて知ったのです。一方で、祖父からは農薬を使わずに植物を育てる方法を学びました。自然と向き合い、手をかけ、見守る——その静かな営みは、今も彼女の作品のなかに息づいています。自然は決して前に出ることはありませんが、彼女の表現にそっと寄り添い、豊かな奥行きをもたらしているのです。
イリアの創作は、ひとつの技法や枠に収まることなく、絶えずかたちを変えながら続いてきました。けれども若い頃は、理解されず、冷ややかな視線や心ない言葉にさらされる日々もありました。詩や絵に心を預けながらも、それらは誰にも見せず、自分だけの場所に大切にしまっていたのです。屋根工事の仕事を選んだのも、人目を気にせず過ごせる環境を求めてのことでした。彼女はようやく心を落ち着け、自分自身に向き合う時間を得ることができたのです。そしてその間も、創りたいという衝動は静かに、しかし確かに燃え続けていました。その思いに光を当ててくれたのが、詩を通じて出会った、コロンビア大学出身の芸術家ラルフ・E・グライムスでした。彼に送ったドローイングは自宅に飾られ、その作品に心を動かされた人がいると知らされたのです。その言葉が、彼女の中に眠っていた自信を呼び覚ましました。1987年、最初の絵画『コジ・ファン・トゥッティ(Cosi Fan Tutti)』が売れたことをきっかけに、彼女の創作は外の世界へと開かれていきます。直感と技術、そして観る人の感情に深く触れる感性。それらが重なり合いながら、彼女は自らの表現を育てていきました。
イリアにとってアートとは、自分を語るためだけのものではありません。人のなかに眠る創造の声を目覚めさせること——それが彼女の創作の根底にあります。「誰かが創りはじめると、その熱は周囲にも伝わっていく」。そう信じる彼女は、アーティストたちに寄り添いながら、彼らが継続的に活動を続けられるよう支えてきました。背中を押し、ともに場をつくってきたその姿勢は、単なる支援を超えて、創り手たちが互いに響き合い、高め合える関係を築く礎となっています。イリアの静かな情熱は、今もなお、見えない火を灯すように、誰かの中の表現を照らし続けています。
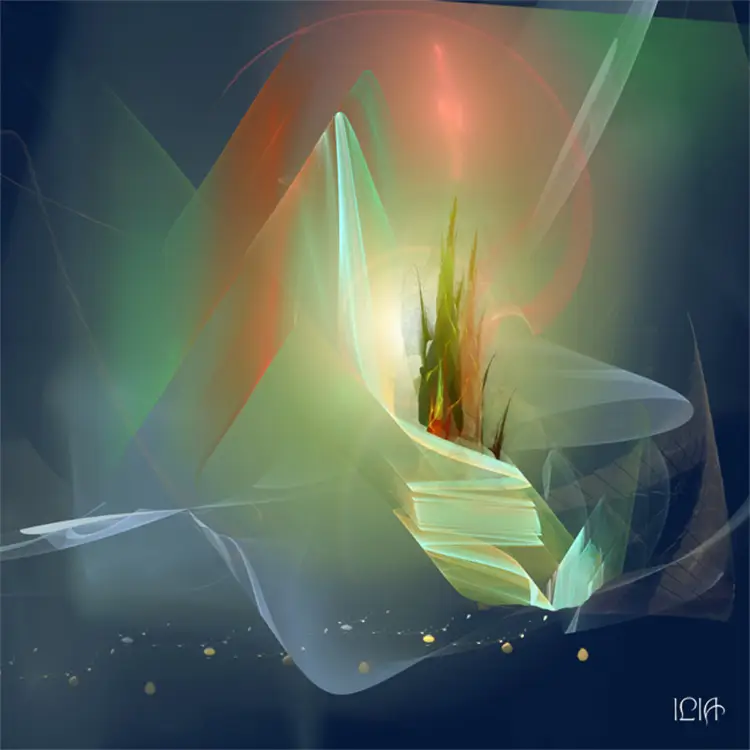
イリア:光が描く、夢の設計図
イリアの作品を特徴づけるのが、彼女自身が「ドリームスケープ(夢の風景)」と名づけたデジタル・ファインアートの手法です。「もし、こんなことができたら?」という小さな問いから始まるこの表現は、あらかじめ完成図を思い描くのではなく、ひとつひとつの要素を重ねながら、まるで視覚の交響曲のように組み上げられていきます。完成までには50時間から100時間ほどを要することもあり、細部まで丁寧に磨き込まれていきます。仕上がったドリームスケープを前に、イリアは人々の反応を見つめます。心からの反応が感じられたとき、その作品は「核」となるコレクションに加えられるのです。彼女のアートは、ただのピクセルではなく、人とのつながりや記憶、そして伝えたい思いを宿すものとして存在しています。
ドリームスケープは、彼女の存在感をデジタルアートの世界で際立たせていますが、イリアの素材への探究心はそれだけにとどまりません。鉛筆、木炭、パステル、アクリル、油彩、そして長年親しんできたアクリルインクなど、多様な画材を使用してきました。そんな彼女がデジタル表現の可能性を見出したのは、他のアーティストのためにウェブサイトやグラフィックを手がける仕事の中で、既存の枠にとらわれない方法でツールを試したことがきっかけでした。そこから独自の技法が生まれ、従来のどれとも異なる質感と感触を持ったデジタル・ファインアートとして結実していきます。音楽や詩の影響も色濃く反映された彼女の作品は、問いかけや感情、そして無意識からのささやきを織り交ぜた、視覚によるひとつの言語のような世界を描き出しています。
イリアの創作は、視覚表現と文章のあいだを行き来しながら、ひとつの対話として広がっていきます。絵だけでも、ことばだけでもなく、その両方が響き合うことで、より深い表現が生まれるのです。発表を予定している書籍には、『メンタリングの技法』『老いた芸術家と吸血鬼』『ルーファーになった私』といったタイトルが並びます。これらの作品は、若い世代への手引きであると同時に、自身の表現の道のりを記した記録でもあります。どのタイトルにも、心の奥に広がる風景や積み重ねてきた時間がにじみ出ており、文章という手段を通して彼女のアートはさらに奥行きを増していきます。イリアにとって、芸術とことばは切り離せないもの。描かれる線も、綴られる言葉も、そのすべてが、観る人・読む人の内側にある何かをそっと目覚めさせるためにあるのです。
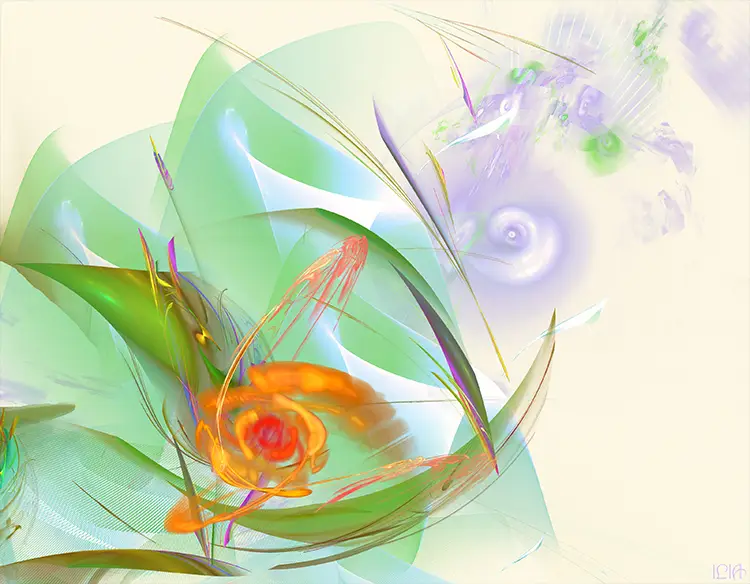
音、静寂、そして空間に宿るひらめき
イリアにとって創作とは、五感すべてを使う体験です。音楽はただのBGMではなく、彼女の表現に寄り添う共演者のような存在。ドリームスケープを描くときも、筆を動かすときも、クラシックやヴィンテージ・ジャズの旋律が、アトリエの空気に感情の色を染み込ませていきます。モーツァルト、ヴィヴァルディ、ベートーヴェン、そしてジャン=ピエール・ランパルのフルート。その音色が、静かに思索を深める空気を運んできます。こうした音の流れは、制作のリズムや筆づかい、作品に漂う感情の陰影にまで影響を与えているのです。視覚と聴覚が調和することで、彼女の制作過程にも、完成した作品にも、奥行きと一体感が生まれます。
彼女の制作環境は、ひらめきと落ち着きがそっと芽生えるよう、丁寧にしつらえられています。壁にはこれまで手がけた作品が飾られ、過去の創作の記憶が静かに励ましを与えてくれます。空間には小さなものたちが息づき、さりげない個性を添えています。窓の外では、小鳥やリス、野良猫、そして最近現れた一匹のウサギが暮らしていて、日々にささやかな動きと命の気配を添えています。手をかけて整えた空間と、自然の気まぐれがほどよく混ざり合うことで、この場所は「生きているアトリエ」として息づき、創作をそっと後押ししてくれるのです。
集中を保つために、イリアはテクノロジーとの距離の取り方にも明確な工夫をしています。絶え間ない情報の波にのまれないよう、機器の使い方を明確に分けているのです。アート制作専用のコンピュータはネットに接続せず、文章は別の端末で執筆。マーケティングや連絡、SNSはさらに別の機器で対応します。こうして役割を切り分けることで、作業効率が上がるだけでなく、気づかぬうちに心がすり減っていくのを防げます。整えられたこの仕組みは、創作の流れをそっと守ってくれます。同時に、繊細で壊れやすいインスピレーションを受けとめる、静かな受け皿でもあるのです。
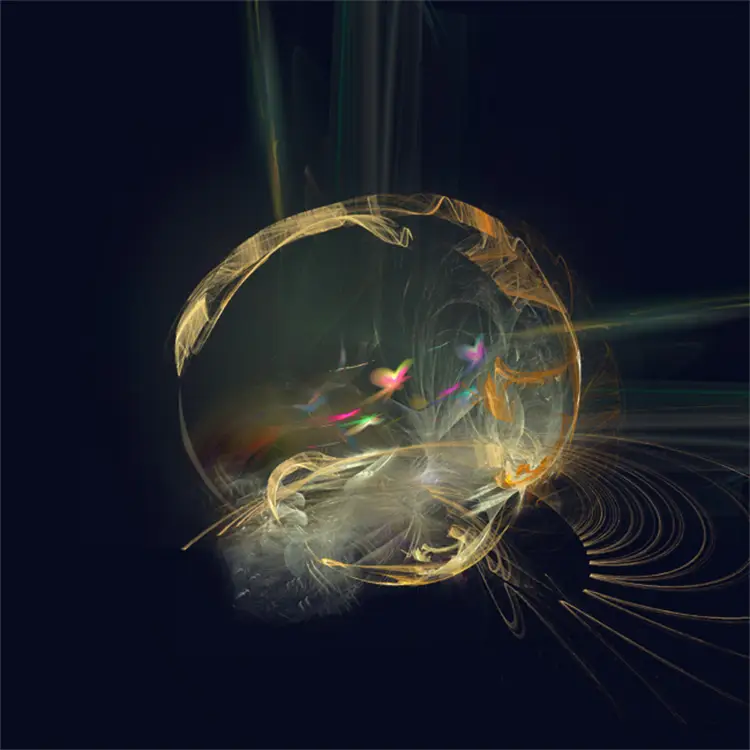
イリア:想像が環境へと変わる場所
イリアの創作に影響を与えてきたものは、分野も時代も多岐にわたります。L・ロン・ハバードの論理的な哲学は彼女の世界観に深く根づき、チック・コリアの没入感あふれる音楽性や、デヴィッド・ポメランツの観客を惹きつけるエネルギーも、大きな刺激となりました。視覚表現の面では、グラミー賞を受賞しディズニーとの協働歴もあるジム・ウォーレンの物語性あふれる作品、そしてゴッホの筆づかいに宿る情熱が、彼女の感性に深く刻まれています。こうした存在は、ただの刺激ではなく、彼女の中に確かな羅針盤を築いてくれました。それは、美しさを生み出すだけでなく、観る人の心をひらき、感性を揺さぶるような表現へと導いてくれるものだったのです。
ラルフ・E・グライムスは、そんな彼女にとって、師であると同時に新しい扉を指し示す存在でもありました。初期の作品を正当に評価し、彼女の中にあった可能性を信じる力を育ててくれたのです。彼の言葉は、ただの称賛にとどまらず、自分の作品には、技巧を超えたもの――現実を見つめ直す視点があるのだと気づかせてくれました。彼が用いた正しさを承認するという独自のフィードバックの手法は、他者の力を引き出そうとする彼女の在り方と通じ合うものがありました。ハバードの創作哲学と重なり合いながら、こうした影響が、彼女を表現と思想が自然に交わる場所へと導いてくれたのです。そこでは、一枚の絵も、一行の言葉も、ただの表現ではなく、何かを伝える手段として息づいています。
いまイリアが思い描いているのは、作品の中に入り込めるような、五感で味わう空間です。ドリームスケープをキャンバスの中にとどめるのではなく、現実の環境として立ち上げたい。植物や動物、音、デジタルアートがひとつに溶け合い、訪れた人がその世界に身を委ねられるような場。そこでは、ただ「観る」のではなく、「包まれる」体験が生まれます。それは、心をやさしく解きほぐすような、発見と癒しの場。観る人ひとりひとりがその空間の一部となり、イリアの広がり続ける景色に、そっと溶け込んでいくのです。