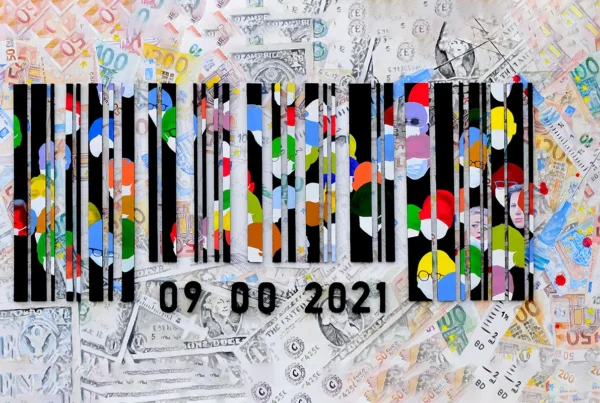「キャンバスに絵を描くより、キャンバスを作るほうが楽しかった。」
思いがけない地図:サッカー場からアトリエへ
ナタリー・ダナム(Natalie Dunham)が創作の道へ進むことになったのは、予期せぬかたちでスポーツの世界を退かざるを得なくなったことがきっかけでした。子どものころ、彼女は「アーティストになりたい」と8歳の自筆で書き残しています。その一方でサッカーにも打ち込み、奨学金を得て大学に進学しました。しかし足首の手術を5度繰り返し、競技を断念せざるを得なくなります。この出来事が、彼女を新たな方向へと導きました。大学のアスレチック・ディレクターの計らいで、キャンパス内の仕事に就くことで奨学金を維持できることになり、最初は事務補助、のちにアートギャラリーの助手を務めました。やがてその経験を通じて、美術の世界へと惹かれていきます。
こうしてダナムは専攻をビジネスから美術へと切り替え、2007年にアラバマ州のバーミングハム・サザン大学で美術学士を取得しました。ただ、彼女が惹かれていたのは絵の具や筆そのものではありません。新しいキャンバスを作るために木枠を組んでいたとき、描くこと以上にその作業自体に心を奪われている自分に気づいたのです。この感覚に背中を押され、彼女は1年をかけて彫刻作品のポートフォリオを制作しました。そしてメリーランド美術大学の大学院に進学し、2010年に彫刻で修士号を取得します。現在はアメリカとヨーロッパの両方にスタジオを構え、国内外で作品を発表しています。
アスリートから彫刻家へ――これは単なる進路変更の物語ではありません。「過程には、結果と同じだけの意味がある」。その信念は彼女の人生に色濃く刻まれています。何をつくるかを最初から決めるのではなく、手を動かす中で形を見つけていく。制作で大切なのは完成ではなく過程だという考えが、彼女の作品の根底に流れています。ナタリー・ダナムの歩みは語りかけます。何かを手放したとき、まったく新しいものが生まれることがあるのだと。

ナタリー・ダナム:構造を彫り、意味を重ねる
ナタリー・ダナムの表現は、構造への探究心を起点に、反復と実験を通じて展開していきます。彼女の彫刻やインスタレーションは、幾何学的なかたちと線の構成を基盤とし、素材を集め、積み重ね、何層にも重ねるプロセスによって形づくられていきます。
ダナムにとって、プロセスは結果に至る手段ではなく、作品の中心にあるものです。制作の過程や構造をあえて見せることで、作家は「つくり手」であると同時に「探求者」としての姿を浮かび上がらせます。彼女の作品は、観る側にも時間をかけることを求めます。ただ目に映るものだけでなく、それがどのようにして生まれたのかを見つめてほしい——そう語りかけてくるのです。基本的なかたちを繰り返し扱いながら、秩序とリズムを感じさせる構成を生み出しつつも、そこには常に変化や揺らぎが残されています。加え、積み、重ねる。その積層の過程は、ひとつの思考が次の思考へと連なり、やがて形が見えてくる。そんな思考の流れにも重なって見えます。
彼女の彫刻やインスタレーションが印象に残るのは、素朴な素材や見慣れたかたちから出発しながらも、作品全体に深みと重さが感じられるところにあります。何気ないものを、特別な存在へと変えていく。まさにそこに、ダナムが伝えようとしている本質があります。制約のなかから美を引き出すこと。ごく小さな要素であっても、繰り返しやスケール、配置によって新たな意味が生まれること。彼女にとって制作とは、かたちや構造、空間を通じて語られる、静かな物語でもあるのです。

秩序が生むもの:プロセスの精度
ダナムの制作環境は、作品そのものと同じくらい綿密に整えられています。スタジオにあるものはすべて所定の場所に収まり、素材にはひとつひとつラベルが付けられています。整理された空間は、見た目のためでも、完璧を求めるためでもありません。集中できる心の余白をつくるための、ごく実践的な手段なのです。彼女は「散らかったスタジオほどやる気を失わせるものはない」と語ります。こうした空間の組み立て方は、作品づくりのプロセスそのものとも重なります。計画的に、意図を持って、そして十分な準備ができてからこそ、直感が生かせる。そうした考え方が、制作のすみずみにまで貫かれているのです。
素材に対する姿勢も、自由でありながら無秩序ではありません。幅広いメディウムを扱ってきたなかでも、彼女がもっとも親しんできたのは彫刻とインスタレーションです。最初は絵画を制作していましたが、次第に「組み立てる」「構成する」といった感覚に惹かれ、より立体的な表現へと移行していきました。大学の卒業制作展では、すでに展示の中心がキャンバスではなく、彫刻やドローイングに移っていたと言います。彫刻の触覚的で空間的な特質は、観る人を身体的にも知的にも引き込みたいという彼女の思いに応えるものです。彼女が三次元の表現にこだわるのは、アイデアをただ「観る」のではなく、「その場に身を置いて感じる」ものとして扱いたいからです。
こうした志向は、作品を設置する空間にも及びます。彼女が描いた構想の多くは、まだ実現していません。それは想像力が足りないからではなく、必要とされる空間がまだ見つかっていないからです。高い天井、広い壁面、開放的な床面。吊り下げ型のインスタレーションを実現するには、そうした条件が不可欠です。今もスケッチブックやメモのなかに眠るこれらの作品案は、ふさわしい場所とタイミングを静かに待ち続けているのです。彼女の制作を支えているのは、スケールの大きさと創造への野心です。その追求はいつも、観る者を引き込み、表現を高め、構造にも力強さを宿しています。

ナタリー・ダナム:数字で綴るクロニクル
ダナムの作品番号は、飾りではなく、制作を支える仕組みそのものです。どの作品にも一つずつ番号が振られていますが、それは偶然ではなく、使われた素材や手法を記録する独自のコードです。数字は、その作品がどのように生まれたのかを示す印であり、同時に時間の足跡でもあります。まるで脚注のように、作品の奥にある構造や思考の道筋へと、観る人を静かに導いてくれます。
ダナムは番号を振ることで、作品に決まった物語を与えようとはしません。むしろその数字は、全体をゆるやかにつなぐ静かな手がかりとなり、一見関係のない作品同士に目に見えない連続性を生み出しています。
この姿勢には、「アートは感覚だけでなく、思考も刺激するものであってほしい」という彼女の信念が込められています。作品の意味をこちらから語るのではなく、観る人が自分で気づき、考え、問いを立てていく。番号という曖昧なタイトルは、そんな自由な解釈を促します。それが制作順なのか、暗号のような記号なのか、それともただの整理番号なのか。明確に答えが与えられていないからこそ、問いが生まれ、複数の見方がひらかれていくのです。ダナムは観る人を、受け身の鑑賞者としてではなく、自分自身の視点で意味を見出す存在として作品に関わってほしいと考えています。
数字の整理や素材の積み上げ方、整然としたスタジオの様子だけを見ると、彼女は秩序にこだわる作家のように見えるかもしれません。けれど実際には、その中に思いがけない変化を受け入れる余白がしっかりと用意されています。慎重に選んだ素材であっても、組み合わせ方によっては思いもよらない反応を見せることがあり、作品のかたちは試行錯誤を重ねながら少しずつ変わっていきます。計画と柔軟さ、構造と偶然。そのあいだの緊張感のなかにこそ、彼女の作品はもっとも深く息づいています。そこにあるのは、ひとつの答えではなく、問いかけそのものです。プロセスとは何か、かたちはどう変わっていくのか、そして私たちは時間のなかで、どのように意味を積み上げていくのか——ダナムの作品は、そうした問いを私たちに静かに差し出しているのです。